春に山の登山口や自然の中で生えてくる山菜。代表的な山菜はわらびがあります。よく春から初夏にかけて山道などで見かけてGW中の行楽に山菜採りで楽しむ方も少なくありません。花がたくさん咲く季節を迎えて山菜を採るかたも見かけるようになりました。
山菜はやタケノコは山野の植物だけにあくが強いものが多くて手間が少し必要になります。わらびもあくの成分は毒性が強いピロリジンアルカロイド類が含まれています。必ずしっかりあく抜きして美味しく食べましょう。
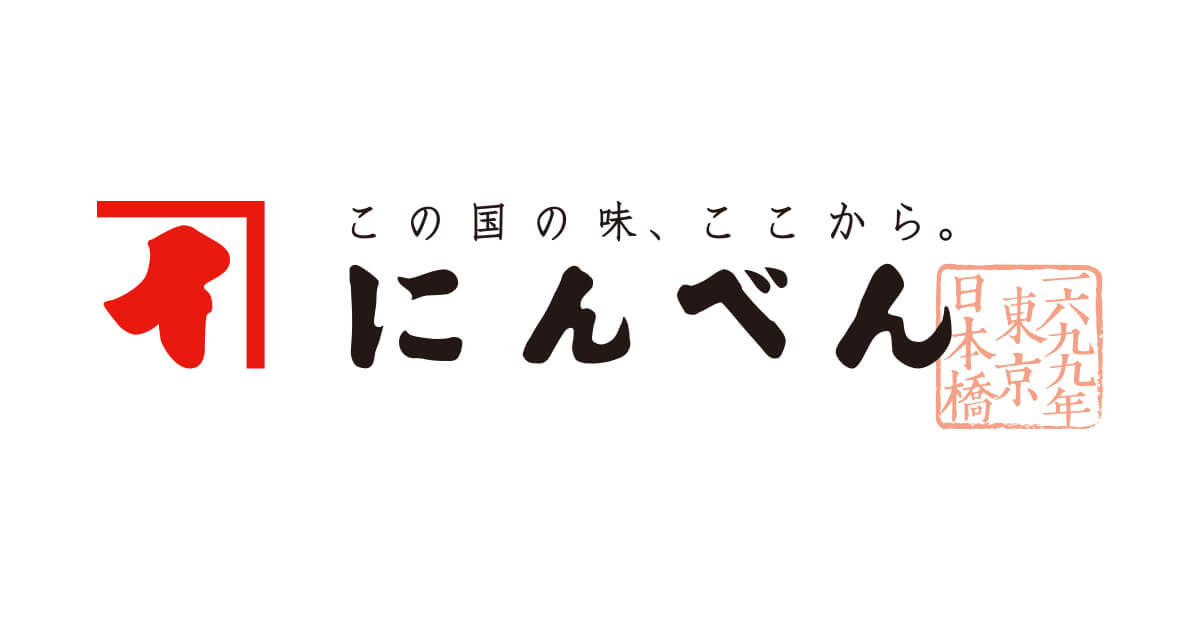
わらびはあく抜きが失敗しやすいのが難点ですがお湯を使うだけで簡単にあく抜きできます。お湯だけで簡単にあくを抜くやり方をご紹介します。
なぜ重曹を入れたお湯だけでわらびのあく抜きは失敗するのか

わらびのあく抜き方法として一般的なのが、沸騰したお湯の中に重曹を入れて茹でるやり方です。
重曹を入れて茹でるという工程で単純に見えますが、わらびがクタクタになってしまい上手くいかない事もよくあります。私も何度も失敗しました。
それからあく抜きの失敗した原因を調べてみました。わらびに合う加熱の仕方や重曹の量の加減をきちんと把握していないのが一番の原因だからです。
あく抜きの時の重曹の量が多すぎたり、茹でる時間がちょっとでも長いと失敗し易くなります。むしろ茹でないやり方が上手く出来ます。
そこで、お湯で簡単につけるだけで簡単にあく抜きするやり方を取り上げていきます。
わらびのあく抜きはお湯だけでなく重曹を振りかけて置くこと

私がわらびのあく抜きをお湯だけで上手くいった手順を書いていきます。わらびの量は200gで計算しています。
①鍋でお湯を沸かす。沸騰したら少し冷まして置く
②お湯を沸かしながら、わらびをサッと洗って汚れを取る。その際根元を切って落とす。わらびの根元は固くて食べられないので切り落としておきます。
③わらびをボール等に入れたら重曹を10g振りかける。そこで少し冷ましたお湯を浸るくらいに注いで鍋等の蓋をして半日から1日置きます。
上記の工程でわらびをあく抜きすると、写真のようにきれいにあくを抜くことが出来ます。後はきれいに洗うとそのまま料理をする事が出来ます。
以前、有川浩さんの人気小説『植物図鑑』の中にわらびのあく抜きはお湯だけで出来ると書かれていたのでやってみました。
その時はあまり上手く出来なかったので、再度のあく抜きには重曹を振りかけました。すると綺麗に出来たので、このやり方であく抜きしています。やはり重曹、あるいはベーキングパウダーを使用するやり方が1番だと思います。
重曹はこうしたアク抜きのほかにも、生鮮食品の臭み消しや台所の油汚れ落とし掃除など用途も広いので、台所に常備しておくとなにかと便利ですよ。
わらびのあく抜き、お湯だけで茹でるやり方以外にもやり方はたくさん

わらびのあく抜きをする際、お湯以外のやり方としては米ぬかや米のとぎ汁、木を焼いた後の灰、小麦粉を使うやり方があります。
ここでは、それぞれのやり方について取り上げていきます。これらは、手元に重曹がない場合すぐに使えるやり方です。
米ぬか
米ぬかを使ったやり方ですが、重曹を使ったやり方と同じです。米ぬかとわらびを入れたボールの中に、少し冷ましたお湯を注いで半日から一晩置いてあくを抜いていきます。米ぬかは最近では精米機のそばから持ち帰り自由のところもあるから、ビニール袋に入れて持ち帰り、利用するといいですよ。
米のとぎ汁
このやり方は昔母がよくやっていた方法で、米のとぎ汁を沸かしてその中でわらびを少し茹でていきます。それから水にさらしてから更にあく抜きをしっかりとしていました。これは上述の米ぬかよりも手軽に出来るから、お米をといだ後とぎ汁で簡単にできます。重曹が手元にない時にも楽です。
木灰
これは、木を焼いたり薪ストーブの燃えカスから出た木灰を振りかけて熱湯を注いで一晩置いてあく抜きをするやり方です。昔の家庭では納豆を包んでいた藁を植木鉢の中で燃やして、その灰でわらびのあくを抜いていたそうです。
よくバーベキューをされる方は炭の燃え残りを取って置いておくと時節柄手に入れやすいと思います。
気軽に木灰を作ってみたいと思われたら、使い終わった割りばしや植木の手入れで取った枯葉を植木鉢の中で焼いてみると簡単に出来ます。
椿の葉
私もこの記事を書くにあたり色々調べてみると、椿の葉を使ってわらびのあく抜きをする方法があることを知りました。
沸騰したお湯の中に、わらびと椿の葉を入れて一晩置いておくと綺麗にあくが抜けるそうです。詳細は以下のリンクを貼りますので参考にしていただけたら幸いです。

わらびをお湯だけで簡単にあく抜きして自然の味を楽しもう

春の山菜の代表各のわらび、ほろ苦い味わいは自然の楽しみでもあります。
しかし春の山菜はあくが強いためそのままで食べることは出来ませんが、お湯と重曹、あるいは木灰などを使って時間をかけることであく抜きも簡単にきれいにすることが出来ます。
わらび等の山菜は調理や下ごしらえが難しく考えられがちですが、簡単に出来るので春の食卓に乗せてお楽しみ下さい。

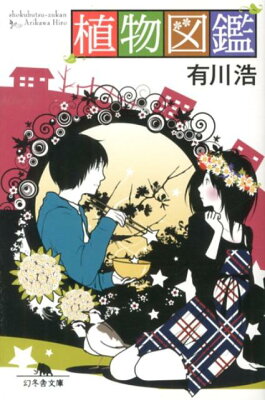



コメント